北海道 東川町 菊地 伸 町長
プロフィール
酪農学園大学卒業後に音楽活動や会社員などを経て、1992年に東川町役場に入庁。交流促進課長、企画総務課長、東川スタイル課長、産業振興課長を歴任。2023年3月より現職。
株式会社ライスレジン 代表取締役COO 奥田 真司
プロフィール
2006年に野村證券株式会社に新卒入社。富裕層向けのリテール業務や上場企業などの法人向けコンサルティング業務を経て、戦略企画業務に従事。2020年5月より、バイオマスレジングループに参画。バイオマスレジン南魚沼 取締役副社長に就任した後、2022年4月に社長執行役員に就任。2024年より株式会社ライスレジン 代表取締役COOに就任。

北海道のほぼ中央、大雪山国立公園の豊かな大自然に囲まれた北海道 東川町。「写真の町」として知られており、良質な地下水にも恵まれています。今回は、北海道東川町 菊地町長とライスレジン代表取締役COO 奥田が「米作りを取り巻く環境変化と課題」をテーマに、対談しました。
豊かな地下水が育む農業と文化的な風土
東川町は1985年に「写真の町」宣言を行い、人と自然・文化が写真を通じて出会う機会を育んでいます。北海道のほぼ中央に位置する人口約8,000人の町ですが、北海道で唯一、上水道がない町でもあります。町民の生活を支えているのが、大雪山が蓄えた雪解け水。この地下水は生活用水としてはもちろんのこと、米作りにも存分に利用されています。2023年にはライスレジンへ加工する資源米の生産をスタート。2024年4月からは、町指定のごみ袋が「ライスレジン」を使用した袋へと変わりました。
奥田:東川町と言えば、有名なものがいろいろあります。その中でも外せないのは「お米」ではないでしょうか?東川町はどのような取り組みをされているのですか?
菊地町長:米作りは開拓当時から、東川町にとってなくてはならない基幹産業でした。それは今でも同じです。東川町はこの30数年で、20%以上も人口が増えています。「持続可能な町になってきた」と言われていますが、その基盤を支えているのは農業ですから。自然豊かな農村景観を作り続けているのも、農業従事者の皆さんです。東川町の良さは、行政、農協、農業従事者が一体となった取り組みができているところ。全国のどの自治体にも負けないのではないでしょうか。そのベースにあるのが、地域の持つポテンシャルだと思います。米作りのための環境や気候、土壌などがすべて好条件で整っている中で、これまでも変わらずに歩み続けてきました。「ライスレジン」の導入を考え始めたのも、こうした地域の連携が深く関わっています。
奥田:ライスレジンについては、当初は農協との連携からスタートしました。その後、さらに資源米を手がけるために東川町や農家の皆さんも加わって、農業全体を支えていこうという想いが三位一体となって広がっていきました。

「米価高騰」は農業のあり方を再考するチャンス
東川町は移住者が増えており、町外からも評価が高いコミュニティへと年々成長しています。移住の理由はさまざまですが、農業従事者が守ってきた「農村景観」に魅せられている方も多いそうです。農業以外の産業で生活している方であっても、素晴らしい農村景観を守るために協力し「東川町ブランド」を維持しようと努力しています。全国的にも東川町が取り組んでいる農業はモデルケースとして注目を集めているのです。一方で「お米を取り巻く環境」は、大きく変化しようとしています。
奥田:先進的な取り組みを進めてきた東川町ですが、現在の「環境の変化」は農業にとって非常に大きな影響があると思います。現在、感じている「農業における課題」は何でしょうか?
菊地町長:やはり日本全体に言えることですが、農業のあり方をもう少ししっかりと考えるべきだと思います。食料自給率の低さはもちろん、それに付随して「日本の将来の見通し」について真剣に向き合わなければなりません。そうしていく中で、東川町の農業のあり方が全国に広まり、理解を深めていければ嬉しいですね。最近では米の価格や流通量が話題になっていますが「生産者は何のために、どういう想いで農産物を作っているのか」を、消費者にも理解すべき時期が来たのではないかと考えています。例えば、米の価格上昇は30〜40年前の価格に戻っただけだという見方もあります。当時は買取価格が60kgで2万円を超えており、現在と同程度の価格だったんです。2万4000〜2万5000円を適正価格として農業従事者が受け取れれば、もっと持続可能な農業が実現できるのではないでしょうか。
この先も地域が一体となって「米作りを中心とする農業を守っていく」という姿勢は、変えないでいたいと考えている東川町。目の前の数字に惑わされず、農業がどのように維持されていくべきかを考えるチャンスと捉えています。
ライスレジンによる農地保全が環境保護に繋がる
東川町は大雪山国立公園を有する、自然豊かな町です。そのため、環境保護への関心も高く「生活用水である地下水を育む環境を守ることが、住民生活を守ることにつながる」という意識が強くあります。ゼロカーボン宣言に取り組む町でもあり、町民も非常に協力的なのだそうです。資源米を活用したライスレジンによるごみ袋の導入は、ゼロカーボンを実現するための取り組みの1つ。2024年からはゼロカーボン実行計画も作り、「ひがしかわカーボンニュートラルフェスタ2024」を開催しました。環境意識をさらに高めるイベントを通じて、町民だけでなく行政や事業者、農協など町全体で関心を持って取り組む風土を作っているそうです。
奥田:ライスレジンは、まさにカーボンニュートラルの“ど真ん中”の取り組みですね。最初にライスレジンを知った時はどのような印象を持たれましたか?
菊地町長:最初は「米を資源としてプラスチック商品に活かす?どういうこと?」と率直に疑問を感じました。「米=食べ物」と思っていましたから。しかし詳しい説明を受けて、すぐに理解できました。農業を持続可能にするためには、農地を守らなければなりません。まさに「米を作り続ける環境を維持する」必要があるんです。いかに米の作付け面積を増やしていけるかが長年の課題であり、そのためにさまざまな苦労の歴史がありました。資源米が生産できれば、環境を維持する手段としては非常に有効です。環境に配慮した取り組みとして、資源米を生産することが、結果として農業の未来につながると感じています。
奥田:そのおかげで、ライスレジンのごみ袋が実現し、導入から2年目を迎えました。町民の方からの反響などは、いかがですか?
菊地町長:変化に対する戸惑いの声はありましたが、批判的な声は上がっていません。全町民から完全に理解を得るのは難しいと思いますから、取り組みを続けながら、少しずつ「私たちが何に取り組んでいるのか」について発信していきたいです。そうした姿勢が、環境保護や、農業への取り組みの理解につながると思っています。
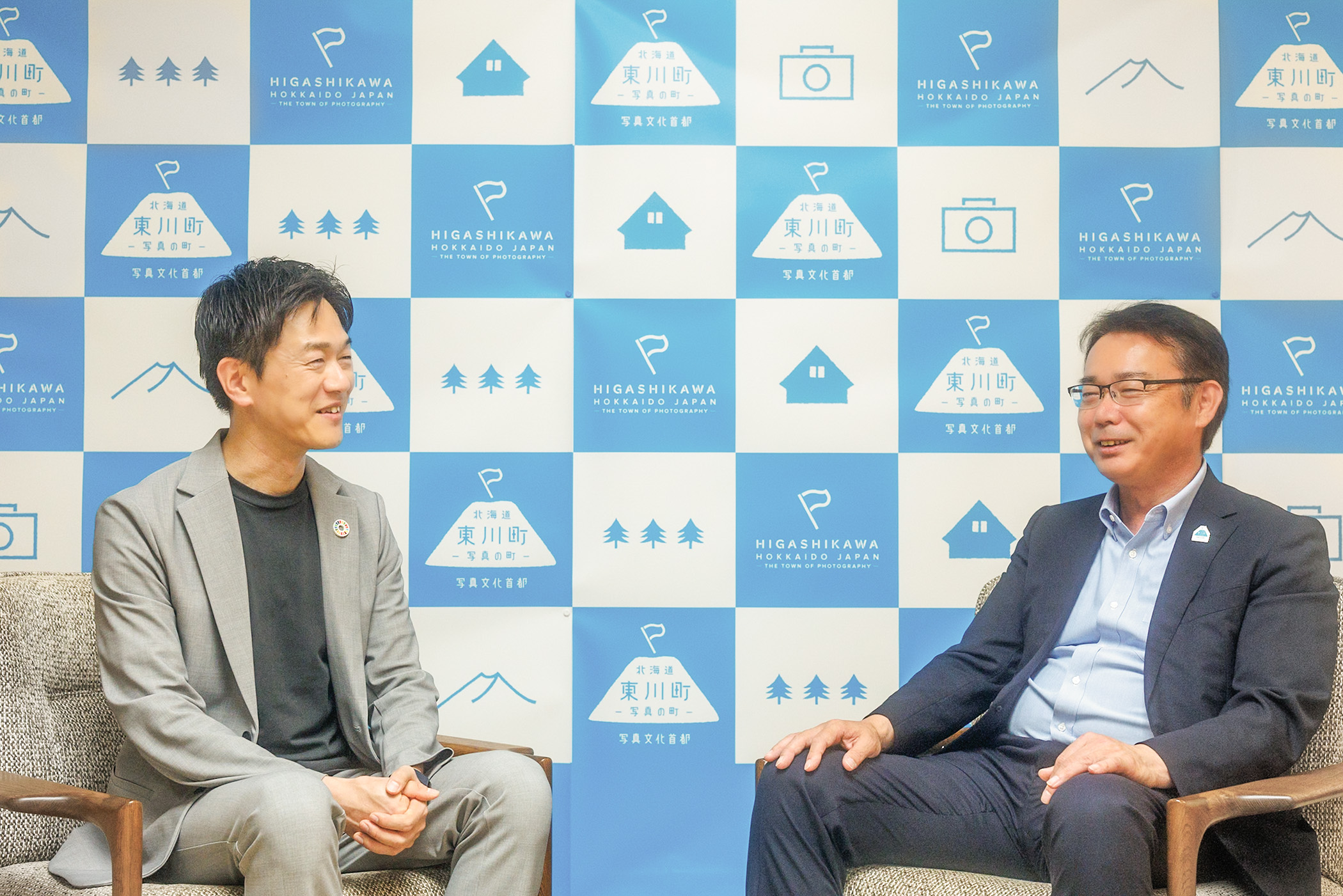
対談を終えて
菊地町長は今後も、ライスレジンを活用した取り組みを継続し、発展させていきたいと考えています。資源米も含めた米作り、そして日本の農業全体への理解を広げることによって、コストダウンも実現できるのではないかと感じているそうです。弊社も東川町でのごみ袋から始まったライスレジンの波を広げるべく、地元の学校給食用食器への導入、地域のホテルや旅館・道の駅などで使用する資材への採用、さらに将来的には農業資材への展開を目指し、共に歩んで参ります。
